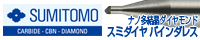会長あいさつ
2010年5月11日の本フォーラム総会および第1回理事会で,会長に選任されました川原田洋です.ニューダイヤモンドフォーラムの設立(1985年),そしてNEWDIAMOND誌創刊(1985年)の翌年から,私はダイヤモンド研究を始めました.自身の研究を育てていただき,また学生教育でも大変お世話になってきたニューダイヤモンドフォーラムでございますので,会長に就任しまして身の引き締まる思いです.会長として,フォーラム全体の動向,私の抱負などをご紹介いたすべきところではございますが,今回は話題を気相合成ダイヤモンド研究周辺に限り,そこから今後の方向を見ていきたいと思います.
1.ダイヤモンド研究の成熟とガラパゴス化
炭素の同素体の研究が,1980年代の気相合成ダイヤモンドの成功を皮切りに活発となった.この20年間でさまざまな純炭素系ナノ材料が登場し,材料研究で常に話題を提供しつづけている.ダイヤモンド,ダイヤモンドライクカーボン(DLC),フラーレン,ナノチューブ,ナノダイヤモンド,グラフェンなどと,同じ炭素でありながら,sp2かsp3結合かの化学結合の選択で,その性質も形も大きく変化する.ダイヤモンド相のみとなるよう努力した筆者にとって,その発生を抑制した相であるグラフェン研究を,大変興味深く見ている.三次元のダイヤモンドから擬一次元のナノチューブまで低次元になったのに,グラフェンで二次元に逆戻りとの印象もある.しかし,デバイスとして一次元より扱いやすい二次元構造に産業界も含め多くの研究者が注目している.現在,グラフェン研究を支えているのは,比較的容易な合成技術と未知の物性への期待である.この二つは,材料研究推進に重要な要素である.ダイヤモンドの研究でもこのような時期は1980年代後半にあった.それはちょうど,筆者自身がダイヤモンドを始めたころでもある.当時の研究内容は現在の水準と比べてあら削りではあったが,新物質に新たな物性を期待する研究者の熱い思い,聴衆の関心の高さは現在のグラフェンと共通していた.1987年の応用物理学会のシンポジウムでは数百名収容の大講堂もいっぱいにする参加者がいたと記憶している.海外,特に米国はもっと熱しやすく(同時に冷めやすく?),同年秋のMaterialsResearchSocietyでは高温超伝導にも負けないぐらいの興味を引いていた.その後,フラーレン,カーボンナノチューブ,そして最近のグラフェンに人気を奪われるが,ダイヤモンドの研究自体は着実に進歩している.研究人口の変動もあまりないが,毎年何か新しい話題が出現している.参加者300名規模の国際会議や大規模学会でのシンポジウムが年間3~4回はある.この中で日本の研究者の役割は大きく,結晶成長,ドーピング,表面界面物性,デバイスなどで主導的な役割を担っている.解決すべき問題は多いが,研究手法が高度となり,内容は洗練され,米国アジア系の先陣争いの熱気というより,欧州日本系の落ち着いた精緻な研究分野となっている.ほかの材料研究者から見ると,やや取っつきにくい物質ということになるかもしれない.合成方法が限られていることがその原因である.
2.ニューダイヤモンドの合成方法,装置の開発
ポピュラーな合成方法は新たな研究者の参入に不可欠である.1980年代から90年代に,高温高圧合成法だけの状況から気相合成方法の出現でダイヤモンド研究者が一挙に増え,新たな物性探索やデバイス開発が始まった.当時は新たな合成条件探索も盛んであった.われわれもダイヤモンド気相合成をより低圧で行おうと,電子サイクロトロン共鳴条件の高密密度プラズマで成膜を行うというそれまでにない方法を開発した.従来圧力(10Torr以上)の1/100~1/1000の圧力(10-2~10-1Torr)でダイヤモンドが合成可能となった.ただ成膜速度は低く,装置も特殊なため主流とはならなかった.しかし,1990年後半から出現したナノダイヤモンド合成において低圧合成が注目され,新たな研究者が参入し,過去のわれわれの結果も低圧大面積合成という点では貢献できた.単結晶の気相合成ダイヤモンド研究では今でも1980年代後半に開発された合成装置が定番となっている.新たな装置開発を行ったグループがこの10年ほとんどなく,まして,新しい原理でダイヤモンド合成に挑戦する研究は皆無といえる.常に新奇な合成装置や新たな物理化学条件での合成がないと,「これまでにないダイヤモンド」,つまり「ニューダイヤモンド」は出現しない.半導体デバイスやディスプレイ産業において発展著しいアジア諸国の製造ラインにおいて,製造装置の根幹をなす薄膜合成装置ではいまだに日本が優位であると聞く.DLCの製造方法についても日本の技術レベルは高い.このような基盤技術を背景に,研究のイニシアティブの維持するために,これまでにないダイヤモンド合成方法,できればより簡単な方法の開発が望まれる.カーボンナノチューブ合成にならった触媒金属を利用したダイヤモンド低温薄膜成長などの試みがあってもよい.
3.ニューダイヤモンドを生かす異種原子,ヘテロ界面の探索
筆者の専門である半導体応用を見ると,ダイヤモンドはまだまだフロンティア研究が残っている.ダイヤモンドで現在期待される低損失パワーデバイスを考えると,必要なのは,1)p形,n形を問わず室温で十分にキャリヤが発生する不純物ドーピング技術,2)高温にも耐える低表面準位密度の表面界面形成技術,3)ダイヤモンド上での高品位絶縁膜やナイトライドとのヘテロ接合形成技術などである.この中には,非常に難しい技術も,あまり行われてれていない研究,すでに開始されたテーマもあるが,うまくいけばダイヤモンドの発展に大きな貢献ができる.ドーピングなしでも室温で表面近傍に十分なキャリヤがあればダイヤモンドは最先端トランジスタに匹敵する性能を示すことが水素終端技術によりわかった.次の段階はより熱的に安定な異種原子の表面技術で同様の結果を再現することにある.ダイヤモンド単体ではなく,異種原子との結合,異種材料との接合が重要で,高品位絶縁膜や半導体膜のヘテロ接合形成がポテンシャルを引き出すうえで不可欠となる.炭素だけを考えるのでなく,ほかの原子の挙動にも十分な配慮が必要であり,その上に立った合成手法の開発が急務である.DLCでSi原子の役割がsp3構造の維持や表面Si-OH形成による低摩擦化と結びついているのは格好のお手本といえよう.ボロン,リンが確実にpおよびn形半導体を制御できることはこの20年間の研究で確認された.しかし,室温で十分なキャリヤが発生可能な浅いアクセプタ,ドナーはまだ発見されていない.どちらかでも見つかればオン抵抗が非常に低くなり,SiCやGaNを超えるパワートランジスタやダイオードの見通しが明るくなる.異種原子の制御は,アクセプタ高濃度領域での超伝導発現や窒素-空孔対の核スピンによる量子ビット形成にも結びつき,これらの物性は超伝導デバイスや量子コンピューティングに発展する.固体物理上,興味深い物性を内包しているダイヤモンドのこれまでにない姿をぜひ見てみたい.

■略 歴
1980 年 早稲田大学大学院理工学研究科修士課程修了
1980 ~ 82 年 (株)日立製作所半導体事業部勤務
1985 年 早稲田大学理工学研究科博士課程修了
1986 年 大阪大学工学部助手
1990 年 早稲田大学理工学部助教授
1995 年 早稲田大学理工学部教授
1995 ~ 96 年 ドイツ・フンボルト財団研究員
(フラウンホーハー研究所応用固体物理部門)
1998 ~ 2003 年 JST CREST(戦略的基礎推進事業)
「表面吸着原子制御による極微細ダイヤモンドデバイス」
研究代表者
現 在 早稲田大学理工学術院教授,ナノ理工学研究機構長
■主として行っている研究
ダイヤモンド,カーボンナノチューブの合成,
物性制御,デバイス応用に関する研究